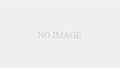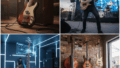【磯部寛之】[Alexandros] 始めに
磯部寛之は日本のロックバンド[Alexandros]のベーシストとして、バンドの重厚なサウンドを支える中核を担っています。彼のプレイスタイルは、正確なリズムキープと力強いグルーヴが特徴で、時に攻撃的なピック弾きを駆使しながらも繊細なフィンガリングも使い分ける多彩なテクニックを持っています。代表曲「ワタリドリ」では疾走感のある16ビートのルート弾きで楽曲全体を推進し、「明日、また」では落ち着いたグルーヴの中にも存在感のある音色を響かせています。
[Alexandros]のサウンドにおいて磯部のベースは、ギターリフとドラムの間を埋める接着剤のような役割を果たしており、楽曲のダイナミクスを生み出す重要な要素となっています。彼の音作りは基本的にシンプルでありながらも、楽曲に応じてエフェクターを効果的に使用し、ロックバンドに必要な迫力と安定感を両立させています。機材選びにおいても実用性を重視し、ライブでの再現性とレコーディングでの表現力を高い次元でバランスさせている点が注目されます。
YouTubeで磯部寛之のプレイをチェック → こちら
使用アンプ一覧と特徴【[Alexandros]・磯部寛之】
磯部寛之はライブとレコーディングで使い分けるアンプセッティングを行っており、主にFender系のアンプを中心に据えています。ライブではパワフルな音圧と明瞭なアタック感を重視したセッティングを施し、大規模な会場でもベースラインがしっかりと聴衆に届くように調整しています。レコーディングでは楽曲の雰囲気に合わせて、温かみのあるヴィンテージトーンから現代的なクリアなサウンドまで幅広く対応できる機材を選択していると想定されます。
アンプヘッドとキャビネットの組み合わせにより、ロック特有の太く芯のある低音を確保しながらも、バンドアンサンブルの中で埋もれない中域の存在感を維持しています。特にFenderのアンプは彼のピック弾きとの相性が良く、アタック音がはっきりと出る点で重宝されていると考えられます。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Bassman | Fender | [Alexandros] | 磯部寛之 | ライブで使用されるメインアンプヘッド | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bassman 810 Cabinet | Fender | [Alexandros] | 磯部寛之 | 8×10インチのキャビネット | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| SVT-VR | Ampeg | [Alexandros] | 磯部寛之 | 真空管アンプヘッド | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| SVT-810E Cabinet | Ampeg | [Alexandros] | 磯部寛之 | Ampegの定番8×10キャビネット | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用ベースの種類と特徴【[Alexandros]・磯部寛之】
磯部寛之は主にFenderのJazz Bassをメイン機材として使用しており、そのクリアで抜けの良いサウンドを活かしたプレイを展開しています。Jazz Bassの2つのシングルコイルピックアップによる明瞭なトーンは、[Alexandros]の楽曲が持つ疾走感とメロディアスな要素を支えるのに最適な選択と言えます。曲によってはPrecision Bassも使用し、よりふくよかで温かみのある低音が必要な楽曲に対応していると想定されます。
彼のベース選びはサウンドの汎用性と演奏性のバランスを重視しており、ライブでの激しい動きにも対応できる信頼性の高いモデルを選択しています。ピックアップのバランス調整により、楽曲のセクションごとに音色を微調整し、イントロやバースでは落ち着いたトーン、サビやブリッジでは前に出る音作りを実現しています。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | ベースの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Vintage Jazz Bass | Fender | [Alexandros] | 磯部寛之 | ジャズベース | メイン使用のヴィンテージ仕様 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| American Professional Jazz Bass | Fender | [Alexandros] | 磯部寛之 | ジャズベース | 現行プロフェッショナルシリーズ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| American Standard Precision Bass | Fender | [Alexandros] | 磯部寛之 | プレシジョンベース | 太い低音が特徴 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Jazz Bass 5 String | Fender | [Alexandros] | 磯部寛之 | 5弦ジャズベース | Low-B弦対応モデル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用エフェクターとボード構成【[Alexandros]・磯部寛之】
磯部寛之のエフェクターボードは、基本的なシグナルチェーンとしてベース本体からチューナー、コンプレッサー、オーバードライブ/ディストーション系、モジュレーション系、そしてアンプへと繋がる構成になっていると想定されます。特にドライブ系のペダルは楽曲の盛り上がりに合わせて使用し、サビやソロセクションで存在感を増すために活用されています。
モジュレーション系エフェクターはコーラスやフランジャーを中心に、楽曲に奥行きと広がりを与える役割を果たしており、アルペジオやメロディアスなフレーズで効果的に使用されています。また、プリアンプを経由することでアンプの特性を補完し、常に安定したトーンを維持できるようにセッティングされていると考えられます。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | エフェクターの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TU-3 Chromatic Tuner | BOSS | [Alexandros] | 磯部寛之 | チューナー | 定番ペダルチューナー | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bass Compressor | MXR | [Alexandros] | 磯部寛之 | コンプレッサー | ダイナミクス調整 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ODB-3 Bass OverDrive | BOSS | [Alexandros] | 磯部寛之 | オーバードライブ | ベース用歪みペダル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bass Big Muff Pi | Electro-Harmonix | [Alexandros] | 磯部寛之 | ファズ | ファズディストーション | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| CEB-3 Bass Chorus | BOSS | [Alexandros] | 磯部寛之 | コーラス | ベース用コーラス | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bass Clone Chorus | Electro-Harmonix | [Alexandros] | 磯部寛之 | コーラス | アナログコーラス | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| SansAmp Bass Driver DI | Tech 21 | [Alexandros] | 磯部寛之 | プリアンプ/アンプシミュレーター | 定番ベースプリアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| GEB-7 Bass Equalizer | BOSS | [Alexandros] | 磯部寛之 | イコライザー | 7バンドグラフィックEQ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| DD-7 Digital Delay | BOSS | [Alexandros] | 磯部寛之 | ディレイ | デジタルディレイ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【[Alexandros]・磯部寛之】
基本EQ設定
磯部寛之の基本的なEQ設定は、低域を適度にブーストしつつ、中域の存在感を確保するバランスの取れたものと想定されます。特に80Hz〜100Hz付近の低域は楽曲の土台となる部分であり、ここをしっかりと確保することでバンドサウンド全体の安定感を生み出しています。中域は400Hz〜800Hz付近を中心に調整し、ギターとの棲み分けを意識しながらもベースラインがはっきりと聴こえるようにセッティングされていると考えられます。
高域については3kHz〜5kHz付近を適度に持ち上げることで、ピック弾きのアタック音を強調し、楽曲の疾走感を演出しています。ただし過度なブーストは避け、耳に刺さらない自然な音色を維持することで、長時間のライブでもリスナーが疲れないサウンドを実現しています。
楽曲別の使い分け
「ワタリドリ」のようなアップテンポでエネルギッシュな楽曲では、ピック弾きを中心としたアタック重視のセッティングを採用し、ドライブ系のエフェクターを適度にかけて前に出るサウンドを作り上げています。一方、「明日、また」のようなミドルテンポの楽曲では、フィンガーピッキングによる温かみのあるトーンを基調とし、コーラスエフェクトで奥行きを加えるアプローチが取られていると想定されます。
バラード系の楽曲ではコンプレッサーの設定を調整し、音の粒を揃えながらも表現力を損なわないよう繊細なダイナミクスコントロールを行っています。楽曲のセクションごとにピックアップのバランスを変えることで、イントロやバースでは落ち着いた音色、サビでは華やかな音色へと変化させる手法も効果的に活用されています。
ミックスでの工夫
レコーディングやミックスの段階では、ベースがバンドサウンド全体の土台としてしっかりと機能するよう、低域の配置に細心の注意が払われています。特にキックドラムとの棲み分けは重要で、キックが担当する超低域とベースが担当する低〜中低域を明確に分けることで、音像がクリアでパワフルなミックスを実現しています。
また、ステレオイメージにおいてはベースを基本的にモノラルでセンターに配置しつつ、コーラスやディレイエフェクトをかけた音を左右に広げることで立体感を演出する手法も取り入れられていると想定されます。ギターが左右に広がるアレンジの中で、ベースが中央でしっかりと支える構造により、[Alexandros]特有の力強くも開放的なサウンドが生み出されています。
比較的安価に音を近づける機材【[Alexandros]・磯部寛之】
磯部寛之のサウンドを比較的安価に再現するためには、まずFender系のJazz Bassタイプのベースを選択することが基本となります。FenderのPlayer SeriesやSquierのClassic Vibeシリーズは、本家の特徴を受け継ぎながらも手の届きやすい価格帯で提供されており、初心者から中級者まで幅広く対応できます。
エフェクターについては、BOSSのベース用ペダルシリーズが信頼性とコストパフォーマンスに優れており、ODB-3やCEB-3といった定番モデルを揃えることで基本的なサウンドメイキングが可能です。アンプについてはFender RumbleシリーズやAmpeg BA Seriesなどのコンボアンプがライブハウスのリハーサルや小規模ライブに十分対応でき、磯部のサウンドに近い音色を得ることができます。
| 種類 | 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | Player Series Jazz Bass | Fender | [Alexandros] | 磯部寛之 | コストパフォーマンス良好 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | Classic Vibe Jazz Bass | Squier | [Alexandros] | 磯部寛之 | ヴィンテージスタイル入門機 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | Rumble 100 Combo | Fender | [Alexandros] | 磯部寛之 | 練習・小規模ライブ向け | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | BA-108 V2 Combo | Ampeg | [Alexandros] | 磯部寛之 | 自宅練習用コンパクトアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | ODB-3 Bass OverDrive | BOSS | [Alexandros] | 磯部寛之 | 定番ベース歪みペダル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | CEB-3 Bass Chorus | BOSS | [Alexandros] | 磯部寛之 | ベース用コーラス | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | Bass Compressor M87 | MXR | [Alexandros] | 磯部寛之 | ダイナミクスコントロール | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
総括まとめ【[Alexandros]・磯部寛之】
磯部寛之のベースサウンドは、シンプルでありながらも確かな技術と音楽性に裏打ちされた、ロックバンドの理想的な低音パートの在り方を示しています。彼の音作りの本質は、楽曲全体を支える土台としての役割を果たしながらも、必要な場面では存在感を発揮するというバランス感覚にあります。Jazz Bassを中心とした機材選択は、クリアで抜けの良いサウンドを確保し、バンドアンサンブルの中で他の楽器と調和しながらも埋もれないという目的を達成しています。
音色の再現において最も重要なのは、機材そのものよりも演奏技術とフレージングへの理解です。磯部のプレイスタイルにおける正確なリズムキープ、適切なダイナミクスコントロール、そして楽曲の雰囲気に応じたピック弾きとフィンガー奏法の使い分けは、どんなに高価な機材を揃えても模倣できない要素です。まずは基本的な演奏技術をしっかりと身につけ、メトロノームと共に練習することで確実なリズム感を養うことが、彼のサウンドに近づく第一歩となります。
エフェクターの使用については、過度に複雑なセッティングを避け、楽曲に必要な音色を的確に選択する姿勢が参考になります。コンプレッサーで音の粒を揃え、ドライブ系で迫力を加え、モジュレーション系で奥行きを出すという基本的なアプローチを理解し、自分の楽曲やバンドサウンドに応じて適切に調整することが重要です。機材に頼りすぎることなく、まずは素の音色を磨き、そこから必要な要素を段階的に加えていくという姿勢が、結果的に説得力のあるサウンドを生み出します。
最終的に、磯部寛之のようなサウンドを目指すには、彼の演奏をよく聴き込み、フレージングやリズムアプローチを分析することが不可欠です。[Alexandros]の楽曲におけるベースラインは決して複雑ではありませんが、楽曲全体の構造を理解し、適切なタイミングで適切な音色を選択する音楽的センスが光っています。この音楽性こそが、機材を超えて真に学ぶべき要素であり、長期的な成長につながる視点と言えるでしょう。
本記事参照サイト【[Alexandros]・磯部寛之】
本記事は下記公式サイト等も参照させていただいております。