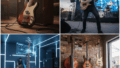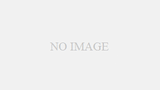【飯田祐馬】KANA-BOON 始めに
飯田祐馬は大阪府出身のベーシストで、KANA-BOONのリズム隊として2008年の結成当初からバンドを支え続けています。彼のベースプレイは、ロックバンドに求められる力強さと存在感を持ちながら、繊細なフレージングや楽曲に寄り添うアプローチが特徴です。指弾きとピック弾きを曲によって使い分け、グルーヴ感と明瞭な音色を両立させています。
KANA-BOONの代表曲「シルエット」「ないものねだり」「フルドライブ」などでは、疾走感のあるロックサウンドを支える骨太なベースラインが印象的です。彼の音作りは、中低域をしっかりと確保しつつも、高音域の抜けを意識した輪郭のはっきりしたトーンが基調となっています。ライブでは安定したリズムキープとダイナミックな演奏で観客を魅了し、レコーディングでは楽曲全体のバランスを見ながら的確なフレーズを構築しています。
使用機材としては、YAMAHAのBBシリーズやLAKLANDといった信頼性の高いベースを中心に、MXRやBOSS、Darkglassなどのエフェクターを組み合わせてサウンドメイクを行っています。アンプはAmpegを主軸にしながら、必要に応じてWalter Woodsなどのハイファイ系も使用するなど、楽曲や会場の特性に応じた柔軟な選択をしています。
YouTubeで飯田祐馬のプレイをチェック → こちら
使用アンプ一覧と特徴【KANA-BOON・飯田祐馬】
飯田祐馬のアンプセレクトは、ライブとレコーディングで異なるアプローチを取っています。ライブではAmpeg SVT-410HEを中心としたキャビネットを使用し、ロックバンドに求められる力強さと音圧を確保しています。ヘッドアンプにはWalter Woods M-450などのハイファイ系も併用することで、クリアで抜けの良い高音域と、タイトな低音域を両立させています。
レコーディングではダイレクトボックスを活用し、Rupert Neve Designs RNDIなどの高品質なDIを通してクリーンかつ解像度の高いサウンドを録音しています。アンプシミュレーターやプリアンプを組み合わせることで、楽曲に最適なトーンを細かく調整する柔軟性を持たせています。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walter Woods M-450 | Walter Woods | KANA-BOON | 飯田祐馬 | ハイファイ系ヘッドアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| SVT-410HE | Ampeg | KANA-BOON | 飯田祐馬 | 4×10キャビネット | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| RNDI | Rupert Neve Designs | KANA-BOON | 飯田祐馬 | 高品質ダイレクトボックス | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用ベースの種類と特徴【KANA-BOON・飯田祐馬】
飯田祐馬のメインベースはYAMAHA BBシリーズで、特にBB2024Xを愛用しています。このモデルはアクティブ/パッシブの切り替えが可能で、幅広いジャンルに対応できる汎用性の高さが魅力です。PU構成はPJ配列を採用しており、プレシジョンタイプの太い低音とジャズベースタイプの明瞭な高音をブレンドできるため、KANA-BOONの楽曲に求められる多様なサウンドを一本で表現できます。
サブベースとしてLAKLANDも使用しており、こちらはよりヴィンテージ寄りのウォームなトーンが特徴です。LAKLANDはジャズベーススタイルのモデルを選択しており、バラード系の楽曲や繊細なフレージングが求められる場面で活躍しています。曲ごとに求められるニュアンスに応じてベースを使い分けることで、アルバム全体のサウンドに多彩な表情を与えています。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | ベースの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB2024X | YAMAHA | KANA-BOON | 飯田祐馬 | アクティブ/パッシブ切替可能ベース | PJ配列、メインベース | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| LAKLAND Jazz Bass | LAKLAND | KANA-BOON | 飯田祐馬 | ジャズベーススタイル | サブベース、ヴィンテージトーン | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| BB424X | YAMAHA | KANA-BOON | 飯田祐馬 | アクティブベース | BBシリーズ関連モデル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用エフェクターとボード構成【KANA-BOON・飯田祐馬】
飯田祐馬のエフェクターボードは、シンプルかつ実用的な構成が特徴です。シグナルチェーンは、ベース本体からMXR M80 BASS DI+に入力し、ここでベースとなる音作りを行います。その後、BOSS BB-1XやDarkglass Microtubes B7K Ultra V2などのプリアンプ/ディストーション系ペダルを通過させ、楽曲に応じて歪みやドライブ感を追加します。
最終的にはダイレクトボックスを経由してミキサーやアンプヘッドに送られ、ライブでもレコーディングでも安定したトーンを確保しています。エフェクターは必要最低限に絞り込まれており、サウンドの核となる部分を確実にコントロールできる構成となっています。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | エフェクターの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M80 BASS DI+ | MXR | KANA-BOON | 飯田祐馬 | プリアンプ/アンプシミュレーター | ベース音作りの核 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| BB-1X | BOSS | KANA-BOON | 飯田祐馬 | ディストーション | ベース専用ディストーション | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Microtubes B7K Ultra V2 | Darkglass | KANA-BOON | 飯田祐馬 | プリアンプ/アンプシミュレーター | モダンディストーション | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【KANA-BOON・飯田祐馬】
基本EQ設定
飯田祐馬の基本的なEQ設定は、低音域を適度に持ち上げつつ、中域と高域でアタック感と輪郭を確保するバランス型です。低音域は80Hz〜120Hz付近をやや強調し、バンドサウンドの土台となる厚みを作り出しています。中域は400Hz〜800Hz付近を調整し、楽曲によって前に出すか引っ込めるかを変えることで、ギターとの棲み分けを図っています。
高音域は2kHz〜5kHz付近をブーストし、指やピックのアタック音をクリアに出すことで、ベースラインの存在感を際立たせています。アクティブベースを使用する際は、プリアンプ側のEQで大まかな調整を行い、エフェクターやアンプで微調整する二段階方式を採用しています。
楽曲別の使い分け
疾走感のあるロックナンバーでは、ピック弾きを中心にアタック重視のセッティングを選択し、BB-1Xなどのディストーション系エフェクターを薄くかけて音の輪郭を強調します。一方、バラードやミディアムテンポの楽曲では指弾きに切り替え、MXR M80のクリーンチャンネルを活用してウォームで丸みのあるトーンを作り出しています。
楽曲のアレンジに応じてベース本体のPU切り替えやトーンノブの調整も積極的に行い、同じ機材でも多彩な表情を引き出す工夫をしています。特にイントロやブレイクダウンなど、ベースが目立つパートでは高域を強調し、リスナーの耳を引きつける演出を意識しています。
ミックスでの工夫
レコーディングにおいては、ダイレクトボックスを通した信号とアンプからのマイク録音を同時に行い、ミックス段階でブレンドすることで立体感と存在感を両立させています。DIからの信号は低音域の明瞭さとアタック感を確保し、アンプからの信号は空気感や倍音成分を補完する役割を担っています。
コンプレッサーは軽めにかけることでダイナミクスを保ちつつ、音量のばらつきを抑えています。ドラムのキックとの棲み分けでは、キックが80Hz以下を担当し、ベースは100Hz〜200Hz付近を主体とすることで、低音域が団子状にならないよう配慮されています。最終的なミックスでは、ギターやボーカルの帯域を避けながらベースの存在感を確保するため、中低域の調整に特に注意を払っています。
比較的安価に音を近づける機材【KANA-BOON・飯田祐馬】
飯田祐馬のサウンドを再現したい初心者ベーシストにとって、YAMAHA BBシリーズのエントリーモデルや、MXR M80 BASS DI+は非常に有効な選択肢となります。BBシリーズはコストパフォーマンスに優れながら、上位モデルと共通する基本設計を持っており、PJ配列による幅広い音色表現が可能です。エフェクターはMXR M80 BASS DI+一台でプリアンプ、EQ、ディストーションを賄えるため、初期投資を抑えながら本格的な音作りができます。
アンプに関しては、小型のコンボアンプでも十分に近いサウンドを得ることができます。重要なのは機材そのものよりも、低域と高域のバランスを意識したEQ調整と、楽曲に応じた奏法の使い分けです。まずは手持ちの機材で基本的な音作りを習得し、徐々にグレードアップしていくアプローチが推奨されます。
| 種類 | 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | BB234 | YAMAHA | KANA-BOON | 飯田祐馬 | BBシリーズエントリーモデル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | BB434 | YAMAHA | KANA-BOON | 飯田祐馬 | BBシリーズ中級モデル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | M80 BASS DI+ | MXR | KANA-BOON | 飯田祐馬 | オールインワンプリアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | BASS DRIVER DI | TECH 21 | KANA-BOON | 飯田祐馬 | M80の代替機 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | ODB-3 | BOSS | KANA-BOON | 飯田祐馬 | エントリーディストーション | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | BA-210 | Ampeg | KANA-BOON | 飯田祐馬 | 自宅練習向けコンボ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
総括まとめ【KANA-BOON・飯田祐馬】
飯田祐馬の音作りの本質は、ロックバンドに求められる力強さと存在感を保ちながら、楽曲全体のバランスを見極める柔軟性にあります。彼のサウンドは決して派手ではありませんが、低音域から高音域まで適切に配分された明瞭なトーンが、KANA-BOONの楽曲に安定した土台を提供しています。機材選択においても、信頼性と汎用性を重視した実用的なセレクトが特徴的です。
再現のポイントとしては、まずベース本体のPU構成とアクティブ/パッシブの切り替えを理解し、楽曲に応じた音色調整を行うことが挙げられます。エフェクターはプリアンプを中心に据え、必要に応じてディストーションやドライブを追加する段階的なアプローチが有効です。EQ設定では低音域の厚みと高音域のアタック感を両立させ、中域で楽器同士の棲み分けを意識することが重要です。
機材に頼りすぎないためには、奏法の基礎を徹底的に固めることが不可欠です。指弾きとピック弾きの使い分け、右手のタッチの強弱、ミュートのコントロールなど、演奏技術そのものがサウンドの質を大きく左右します。高価な機材を揃える前に、手持ちの機材で基本的な音作りを習得し、自分の演奏スタイルに合った調整方法を見つけることが推奨されます。
また、ライブとレコーディングでは求められるサウンドが異なるため、状況に応じた柔軟な対応力を身につけることも大切です。ライブでは音圧と存在感、レコーディングでは解像度と倍音成分といった、それぞれの環境で重視すべきポイントを理解し、機材セッティングを調整する経験を積むことで、飯田祐馬のような説得力のあるベースサウンドに近づくことができます。
最終的には、機材や設定よりも楽曲への理解と自分自身の表現力が最も重要です。KANA-BOONの楽曲を繰り返し聴き込み、ベースラインが果たしている役割を深く理解することで、技術と音楽性の両面から飯田祐馬のサウンドに迫ることができるでしょう。
本記事参照サイト【KANA-BOON・飯田祐馬】
本記事は下記公式サイト等も参照させていただいております。