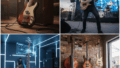【Makoto】BRAHMAN 始めに
BRAHMANのベーシストとして知られるMakotoは、力強いサウンドとダイナミックなプレイスタイルで日本のロックシーンに確固たる位置を築いています。彼のベースラインは重厚でありながらもしなやかさを兼ね備え、バンドのサウンド全体を支える重要な役割を担っています。
Makotoのプレイスタイルの特徴は、TAMAの太く響くドラミングと完璧にシンクロした正確なリズム感にあります。指弾きを中心としたテクニックで繰り出される彼のラインは、ハードコアパンクの激しさとレゲエの粘り気ある質感を巧みに融合させた独自性を持っています。特に低音弦を強く弾く彼の演奏は、BRAHMANのライブパフォーマンスにおいて圧倒的な存在感を放っています。
楽曲においては、「アマテラス」や「不倶戴天」などの代表曲で彼のベースラインがバンドサウンドの骨格を形作っています。特に「BASIS」では、印象的なベースラインが曲全体を牽引し、Makotoの卓越した演奏能力が存分に発揮されています。BRAHMANの楽曲におけるベースの役割は単なるリズムキープを超え、曲の展開やグルーヴ感を左右する重要な要素となっています。
機材面では、ESPのシグネチャーモデル「ESP AMAZE-SL」や「ESP RANDOM STAR Bass」を愛用しており、これらが彼特有の唸るような低音と抜けの良いサウンドを生み出しています。また、アンプやエフェクターの選択にもこだわりを持ち、BRAHMANの楽曲にふさわしい音作りを追求しています。
BRAHMANの音楽性はハードコア、パンク、レゲエなどのジャンルを横断する多様性を持ちながらも、社会的メッセージ性の強い楽曲で知られています。その中でMakotoのベースは、TOSHI-LOWの力強いボーカルとRONZIのギターライン、TAMAのドラミングと完璧に調和し、バンド全体の音楽的結束力を高めています。
YouTubeでMakotoのプレイをチェック → こちら
使用アンプ一覧と特徴【BRAHMAN・Makoto】
BRAHMANのベーシストMakotoは主にAguilar(アギュラー)やAmpeg(アンペグ)のアンプを愛用しています。特にAguilarのTone Hammerシリーズは温かみのある低域とクリアな高域を両立させた音作りができるため、BRAHMANの重厚なサウンドの土台を支えています。
ライブではAguilar DB751やAmpeg SVTといったハイパワーアンプと大型キャビネットの組み合わせで、広いステージでも埋もれないパンチの効いた低音を実現。一方、レコーディングではより繊細な表現が可能なコンパクトなアンプを使い分けることもあります。
サウンドメイクの特徴としては、中低域をしっかり出しつつも高域のアタック感を残す「芯のある音」を追求。BRAHMANの激しいライブパフォーマンスでも安定した音圧と存在感を保ち、TOSHI-LOWのボーカルやRONZIのギターと絶妙なバランスを取っています。
使用アンプ機材表【BRAHMAN・Makoto】
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVT-4PRO | Ampeg | BRAHMAN | Makoto | メインのヘッドアンプとして使用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| SVT-810E | Ampeg | BRAHMAN | Makoto | メインキャビネット、8×10インチ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| JH-1 Jazzmaster | HARTKE | BRAHMAN | Makoto | バックアップとして使用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| DB751 | Aguilar | BRAHMAN | Makoto | 以前使用していたヘッドアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| SANSAMP BASS DRIVER DI | Tech 21 | BRAHMAN | Makoto | プリアンプとして愛用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| 800RB | Ampeg | BRAHMAN | Makoto | 初期に使用していたアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用ベースの種類と特徴【BRAHMAN・Makoto】
BRAHMANのベーシストMakotoは主に国産ブランドESP製のオリジナルモデルを愛用しています。特にESP AMAZE-CTM-4とESP AMAZE CUSTOM BASS “MK BASS”が代表的です。
AMAZE-CTM-4は4弦モデルでASHボディ、ハムバッカーPUを搭載し力強いサウンドを生み出します。一方、MK BASSはALDERボディにEMG社製のPUを装備し、よりパンチの効いたアタックが特徴です。
これらのベースからは太く重心の低いサウンドが得られ、BRAHMANのヘヴィなバンドサウンドを支える重要な要素となっています。特に中低域の豊かな鳴りと歪みに強い特性が、彼の激しいプレイスタイルと相性が良いと言えるでしょう。
使用ベース機材表【BRAHMAN・Makoto】
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | ベースの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESP FOREST BASS | ESP | BRAHMAN | Makoto | PBタイプ | BRAHMANのベーシストとして使用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ESP SIGNATURE SERIES Custom Shop | ESP | BRAHMAN | Makoto | JBタイプ | シグネチャーモデル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ESP AMAZE-CTM7 | ESP | BRAHMAN | Makoto | 5弦ベース | カスタムモデル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| KIKUTANI Contrabass IB-30/WR | KIKUTANI | BRAHMAN | Makoto | アップライトベース | ライブで使用する場合もある | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| A-FACTORY SJB | A-FACTORY | BRAHMAN | Makoto | JBタイプ | A-FACTORYのオーダーメイド | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| FERNANDES RETROSPECT BASS | FERNANDES | BRAHMAN | Makoto | PBタイプ | 初期に使用していた機材 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用エフェクターとボード構成【BRAHMAN・Makoto】
BRAHMANのベーシストMakotoは、パワフルかつキレのあるアンサンブルを支える重要な役割を担っています。彼のサウンドの核となっているのは、EDEN製アンプとESP製ベースの組み合わせです。
エフェクターボードにはMXR Bass D.I.+を中心に、Bass Envelope FilterやBass Octave Deluxeなどが配置されています。これらを駆使して、バンドのヘヴィなサウンドを支える太いベースラインから、ファンキーなフレーズまで多彩なサウンドを生み出しています。
特にBass Compressorを活用することで音量の安定性を確保し、激しいライブパフォーマンスでも安定したサウンドを実現しています。また、BOSS TU-3などの定番機材も取り入れ、実用性と音質の両立を図っています。
使用エフェクター機材表【BRAHMAN・Makoto】
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | エフェクターの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWER-ALL PA-9 | Voodoo Lab | BRAHMAN | Makoto | パワーサプライ | 複数のエフェクターに電源供給 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| GE-7 | BOSS | BRAHMAN | Makoto | イコライザー | 7バンドのイコライザー | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| M5 Stompbox Modeler | LINE6 | BRAHMAN | Makoto | マルチエフェクター | 様々なエフェクトを1台に搭載 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| A/B BOX | MXR | BRAHMAN | Makoto | スイッチングシステム | 2つの信号経路を切り替え | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| CS-3 | BOSS | BRAHMAN | Makoto | コンプレッサー | サステインと音量のバランスを調整 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| FLASHBACK | TC ELECTRONIC | BRAHMAN | Makoto | ディレイ | 多彩なディレイタイプを搭載 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【BRAHMAN・Makoto】
Makotoのベースサウンドは、ESP製の5弦ベースとAmpeg SVTアンプの組み合わせが基本となっている。
EQセッティングは中低域(200-400Hz)を若干持ち上げ、低域(80Hz付近)を適度に残しつつ、高域(2-4kHz)をカットすることで、バンドサウンドの土台となる芯のある音を作り出している。
ライブでは、ダイレクトとマイク収録の両方を併用し、PA卓でのミックス時に状況に応じてバランスを調整している。
楽曲のテンポや強弱によってピッキングの強さを変え、速いパッセージではコンプレッサーのアタックを速め、スローナンバーではリリースを長めに設定するなど繊細な調整を行っている。
「THE VOID」などの重厚な楽曲では低域を強調し、「FOR ONE’S LIFE」のようなグルーヴ感が重要な曲では中域(500-800Hz)を持ち上げてアタック感を引き立てている。
ライブではドラムとの相性を考慮し、キックドラムの倍音と被らないよう200Hz付近を少し削ることもある。
レコーディングでは、トー・コントロールを使い分け、曲の展開に合わせてサウンドにバリエーションをつけている。
ミックス段階では、ベースの定位を中央に固定しつつ、サイドチェイン・コンプレッションでキックドラムとの干渉を避け、低域のパンチを保持している。
また、必要に応じてパラレルコンプレッションを活用し、原音の輪郭を残しながら太さと安定感を両立させ、BRAHMANの重厚かつダイナミックなサウンドの土台を支えている。
比較的安価に音を近づける機材【BRAHMAN・Makoto】
BRAHMANのベーシストMakotoサウンドの核は、ESP製シグネイチャーベースTB-M II/Mとアンプヘッドの組み合わせですが、予算を抑えるならESP/LTD製アクティブピックアップ搭載モデルがおすすめです。TB-M II/Mは40万円を超えるため、AP-4やB-254などの10〜15万円台のモデルで近い音作りが可能です。さらに手頃な価格帯ではESP/LTD B-55やB-104などの5〜8万円台のモデルでも、アクティブ回路と太めの弦を使うことでMakotoサウンドの基礎を作れます。
アンプに関しては、Makotoの愛用するAmegがハイエンドなため、代わりにAmpeg SVTシリーズの小型モデルやMarkbassのLittle Markシリーズなどが予算内の選択肢となります。特にMarkbassは10万円前後から手に入り、クリアでパンチのあるサウンドが特徴です。エフェクターではZoom B1Fourなどのマルチエフェクターを導入することで、コストを抑えながら多彩な音作りが可能になります。
Makoto流の音作りのポイントは、アクティブサーキットによる太くパンチのあるトーンと、ミッドレンジを少し削ってローとハイを強調するEQ設定にあります。弦はDunlop製の太めのゲージ(45-105程度)を使い、ピック弾きとフィンガー弾きを状況に応じて使い分けることで、彼の音色の幅広さを再現できます。また歪みやコンプレッションは控えめに使い、音の芯を残したサウンドメイキングを心がけましょう。
比較的安価に音を近づける機材表【BRAHMAN・Makoto】
| 種類 | 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGIN_ROWS | undefined | undefined | BRAHMAN | Makoto | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | |
| 種類 | 機材名 | メーカー | BRAHMAN | Makoto | 備考 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | AP-4 | ESP/LTD | BRAHMAN | Makoto | 10~15万円台、アクティブピックアップ搭載 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | B-254 | ESP/LTD | BRAHMAN | Makoto | 10~15万円台、アクティブピックアップ搭載 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | B-55 | ESP/LTD | BRAHMAN | Makoto | 5~8万円台、アクティブ回路搭載 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | B-104 | ESP/LTD | BRAHMAN | Makoto | 5~8万円台、アクティブ回路搭載 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | SVTシリーズの小型モデル | Ampeg | BRAHMAN | Makoto | Makotoの使うAmegの代替として | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | Little Markシリーズ | Markbass | BRAHMAN | Makoto | 10万円前後、クリアでパンチのあるサウンド | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | B1Four | Zoom | BRAHMAN | Makoto | マルチエフェクター、コスト抑えて多彩な音作り | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| 弦 | ベース弦(45-105程度) | Dunlop | BRAHMAN | Makoto | 太めのゲージ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| END_ROWS | undefined | undefined | BRAHMAN | Makoto | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
総括まとめ【BRAHMAN・Makoto】
Makotoのベース音作りの核は、歪みと低音の絶妙なバランスにある。激しいロックサウンドの中でも埋もれない存在感と、曲の土台となる低域の安定感を両立させることで、BRAHMANの重厚な音響世界を支えている。
Makotoサウンドを再現するポイントは、アグレッシブなピック弾きと適度なコンプレッションの活用だろう。特に速いパッセージでも音の粒立ちを保ち、バンドサウンド全体にグルーヴ感を与えるアタック感の調整が重要となる。
注目すべきは、Makotoの「音への姿勢」だ。特定の機材に依存するのではなく、自身の演奏スタイルや音楽性を追求し続ける姿勢こそが本質である。テクニックと感性を磨くことが、彼のようなサウンドへの近道になるだろう。
本記事参照サイト【BRAHMAN・Makoto】
本記事は下記公式サイト等を参照して作成しています。