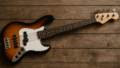【Tamaki Kunish】MONO 始めに
Tamaki Kunish(国島 多真紀)は、日本のポストロック・バンド「MONO」のベーシストとして長年活動してきたミュージシャンです。MONOは1999年に東京で結成され、国際的に高い評価を受けるインストゥルメンタル・バンドとして知られています。
Tamaki Kunishのベーススタイルは、MONOの広大なサウンドスケープを支える重要な要素となっています。彼女の奏でる低音部は、バンドの特徴である壮大なダイナミクスと叙情的な楽曲構成の土台を形成。シンプルながらも強固なベースラインで、ギターやドラムとの絶妙なバランスを保ちながら楽曲の起伏を彩ります。

MONOの音楽性は、ポストロックの枠を超え、現代クラシック、アンビエント、ノイズロックの要素を融合させた独自の表現を追求しています。オーケストラとのコラボレーションも多く、映画的な広がりを持つサウンドが特徴的です。Tamaki Kunishのベースは、そうした壮大な音響空間において、聴き手を包み込むような温かみと、時に激しく波打つような力強さを併せ持っています。
代表曲「Ashes in the Snow」や「Hymn to the Immortal Wind」などでは、彼女の奏でる持続音が楽曲の緊張感と解放感を生み出す重要な役割を担っています。繊細なアルペジオから轟音のクライマックスまで、MONOの音楽の劇的な展開において、Tamaki Kunishのベースは感情の起伏を表現する不可欠な要素となっているのです。
YouTubeでTamaki Kunishのプレイをチェック → こちら
使用アンプ一覧と特徴【MONO・Tamaki Kunish】

MONO(モノ)のベーシストTamaki Kunish(タマキ・クニシ)は、バンドのポストロック/インストゥルメンタルロックサウンドを支える重要な存在です。彼女の使用機材は、MONOの壮大で瞑想的な音楽性に合わせた選定がなされています。
ライブパフォーマンスでは、Ampeg SVT-4PROを主力とし、力強い低域と透明感のある中域を両立させています。一方、スタジオレコーディングではより繊細なニュアンスを表現するため、ヴィンテージアンプも併用することがあります。
Tamakiのベースサウンドは、MONOの楽曲に不可欠な土台となる低域の重厚さと、ギターとの融合を意識した中高域のクリアさを特徴としています。特にバンドの長尺楽曲においては、サスティンの豊かさとダイナミクスの広さが重要視されています。
アンビエントからクレッシェンドに至るMONOの楽曲構成において、彼女のベースサウンドは単なるリズム楽器にとどまらず、楽曲の情感を高める表現手段として機能しています。
使用アンプ機材表【MONO・Tamaki Kunish】
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVT-4PRO | AMPEG | MONO | Tamaki Kunish | メインで使用するアンプヘッド | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| SVT-810E | AMPEG | MONO | Tamaki Kunish | ライブでの迫力ある低音を実現するキャビネット | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| GEQ-1500 | AMPEG | MONO | Tamaki Kunish | サウンド調整用イコライザー | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| VB-1 | DEMETER | MONO | Tamaki Kunish | バルブベースプリアンプ、温かみのある音作り | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bassbone | RADIAL | MONO | Tamaki Kunish | ベース用プリアンプ、ライブでの音色切替に活用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| M2 | MESA/BOOGIE | MONO | Tamaki Kunish | パワフルな音質で時々使用するアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Pro 500 | MARKBASS | MONO | Tamaki Kunish | 軽量で持ち運びに便利なアンプヘッド | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用ベースの種類と特徴【MONO・Tamaki Kunish】

MONO(モノ)のベーシストTamaki Kunishは、主にFenderのJazzBassを愛用していることで知られています。そのJazzBassは彼女の繊細かつダイナミックなプレイスタイルを支える重要な楽器となっています。
MONOのポストロックサウンドにおいて、彼女のベースは豊かな低域の量感と明瞭なミッドレンジが特徴です。特に長いサスティーンと温かみのある音色は、バンドの壮大なサウンドスケープの土台を形成しています。
エフェクターを効果的に使用することで、時には歪ませた攻撃的なトーンから、時には透明感のあるクリーンなサウンドまで、楽曲の感情表現に合わせた多様な音色を生み出しています。MONOの曲の多くで聴かれる重層的なテクスチャーにおいて、彼女のベースラインは音楽の流れを導く重要な役割を果たしています。
使用ベース機材表【MONO・Tamaki Kunish】
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | ベースの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fender Precision Bass | Fender | MONO | Tamaki Kunish | PBタイプ | ロングスケール仕様 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Fender Jazz Bass | Fender | MONO | Tamaki Kunish | JBタイプ | 特殊な弦高調整 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Nash PB | Nash Guitars | MONO | Tamaki Kunish | PBタイプ | ヴィンテージ風のデザイン | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Ampeg Dan Armstrong | Ampeg | MONO | Tamaki Kunish | アクリルボディ | 透明ボディが特徴的 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Rickenbacker 4001 | Rickenbacker | MONO | Tamaki Kunish | セミアコタイプ | 独特のトーン | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Atelier Z M245 | Atelier Z | MONO | Tamaki Kunish | 5弦ベース | 低音域の表現力を重視 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用エフェクターとボード構成【MONO・Tamaki Kunish】

ポストロック/インストゥルメンタルロックバンドMONOのベーシストTamaki Kunishは、バンドの特徴的なサウンドスケープを支える重厚なベースラインを生み出しています。彼女のエフェクトボードには、繊細な音色変化から轟音まで対応できる構成が見られます。
主にディストーション系とモジュレーション系を組み合わせ、MONOの楽曲の特徴である静寂から爆発的なクレッシェンドまでをカバー。また、アンビエント的な広がりを表現するためのリバーブやディレイも効果的に配置されています。
バンドの長尺楽曲において、Tamakiのベースは単なるリズム楽器としてだけでなく、音響的な要素としても重要な役割を果たしています。エフェクトの選定も、楽曲の起伏や感情表現を効果的に引き出すことを念頭に置いていると考えられます。
使用エフェクター機材表【MONO・Tamaki Kunish】
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | エフェクターの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electro-Harmonix Bass Big Muff Pi | Electro-Harmonix | MONO | Tamaki Kunish | ファズ | MONO主要ディストーションペダル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| RAT | ProCo | MONO | Tamaki Kunish | ディストーション | メインで使用するディストーションペダル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| TU-3 | BOSS | MONO | Tamaki Kunish | チューナー | ベースチューニング用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| XP-300 SPACE STATION | Digitech | MONO | Tamaki Kunish | モジュレーション系 | 空間系サウンド生成用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| B.K. BUTLER TUBE DRIVER | B.K. BUTLER | MONO | Tamaki Kunish | オーバードライブ | 真空管プリアンプ搭載 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【MONO・Tamaki Kunish】
MONOのベーシストTamaki Kunishは低域の存在感と中域の輪郭をバランス良く出すため、200Hz付近をわずかにブーストし、500Hz帯を少し削ることで音の濁りを排除している。
ゲインは控えめに設定し、ピッキングの強弱で音量変化をつけることで楽曲のダイナミクスを表現する工夫が特徴的だ。
ライブではコンプレッサーのアタックを遅めに設定し、リリースを早めることで音の立ち上がりを損なわず、サステインを確保している。
楽曲のテイストによって音作りを使い分け、激しい曲では800Hz帯を若干持ち上げてミックス内での存在感を高める。
対照的に静かなパートでは80〜100Hz帯を中心に、低域の量感を重視したEQ設定に切り替えている。
ディストーションを使用する際には3kHz以上の高域をカットし、歪みの刺々しさを抑えつつ芯のある音を作り出す。
また、複雑なフレーズではコンプのスレッショルドを下げ、音量のバラつきを抑制している。
レコーディングでは、ベースの定位を中央よりやや左に配置し、ドラムのキックと周波数が重ならないよう200Hz以下を慎重に調整している。
リバーブは控えめに使用し、音の輪郭をぼやけさせないよう心がけるのがTamakiのこだわりだ。
マスタリング段階では過度な音圧競争を避け、ダイナミクスを残すことで音楽的な起伏を大切にしている。
こうした繊細な音作りの積み重ねが、MONOの壮大なサウンドスケープを支える土台となっているのである。
比較的安価に音を近づける機材【MONO・Tamaki Kunish】
MONO のベースサウンドを手頃な価格で再現するには、楽器と基本的なエフェクターの組み合わせが重要です。Tamaki Kunish のベース音は比較的シンプルながらも繊細な質感を持ち、その雰囲気は適切な機材選びで近づけることができます。中心となるのはプリアンプとコンプレッサーで、特にベースのミッドレンジを強調するタイプのものが効果的でしょう。
具体的な機材では、まず予算内でできるだけ良質なアクティブベースを選ぶことがスタートポイントとなります。次に手頃な価格帯のベースプリアンプとして、EBS Session 60やHartke HD25などが選択肢として挙げられます。エフェクターはMXR Bass Compressorのような2万円前後のコンプレッサーでも十分実用的な音作りが可能です。低予算ながら基本的な音の要素を押さえることで、プロの音に一歩近づけるでしょう。
最終的な音作りでは機材だけでなく演奏技術も重要な要素です。Tamaki Kunishのフィンガリングや音の強弱の付け方などを研究してみましょう。高価な機材に手が届かなくても、基本となる音色を作り出し、そこに自分なりの解釈と技術を加えることで、予算内でも満足度の高いサウンドに近づけることができます。機材の制約はむしろ創造性を刺激する良い機会かもしれません。
比較的安価に音を近づける機材表【MONO・Tamaki Kunish】
| 種類 | 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGIN_ROWS | undefined | undefined | MONO | Tamaki Kunish | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | |
| 種類 | 機材名 | メーカー | MONO | Tamaki Kunish | 備考 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベースアンプ | Session 60 | EBS | MONO | Tamaki Kunish | 手頃な価格帯のベースプリアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベースアンプ | HD25 | Hartke | MONO | Tamaki Kunish | 手頃な価格帯のベースプリアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | Bass Compressor | MXR | MONO | Tamaki Kunish | 2万円前後のコンプレッサー | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| END_ROWS | undefined | undefined | MONO | Tamaki Kunish | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
総括まとめ【MONO・Tamaki Kunish】
Tamaki Kunishの音作りの核は、バンドの壮大な音楽世界を支える重厚な低音にある。ポストロックシーンで独自の地位を築いたMONOのサウンドベースとして、彼女のベースラインは曲の土台となりながらも繊細な表情を見せる。
彼女のサウンド再現のポイントは、音色そのものよりも音の配置と強弱の付け方だろう。激しいクレッシェンドから静謐なパッセージまで、バンドの起伏に寄り添いながらも、要所で存在感を示す演奏スタイルが特徴的だ。
インタビューからは、機材にこだわりながらも本質的には音楽表現を優先する姿勢が伺える。特定の機材に依存するのではなく、自身の表現に必要な要素を見極め、それを実現するためのツールとして機材を選択する実直なアプローチを持っている。
本記事参照サイト【MONO・Tamaki Kunish】
本記事は下記公式サイト等を参照して作成しています。