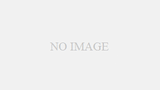KENTA】WANIMA 始めに
WANIMAのベーシストKENTAは、パンクロックやメロディックハードコアに根差した力強いプレイスタイルで知られています。彼のサウンドは明瞭なアタックと太いミドルレンジが特徴で、ドライブ感のあるロックサウンドを作り上げています。代表曲「やってみよう」や「ともに」では、シンプルながらも楽曲を支える骨太なベースラインが印象的です。
KENTAのプレイは、ピック弾きを中心とした攻撃的なアプローチが中心で、バンドのエネルギッシュなサウンドを下から支えています。ESP製のシグネチャーモデル「助平」を愛用し、ライブでもレコーディングでも一貫したサウンドメイキングを心がけていると想定されます。Gallien-Kruegerのアンプを基軸に、明るくパンチのあるトーンを作り出しているのが彼の音作りの特徴です。
シンプルな機材構成ながらも、楽曲に必要な音色を的確に表現する姿勢は、初心者ベーシストにも参考になるでしょう。バンドアンサンブルの中での役割を理解し、ギターやドラムとのバランスを考えた音作りが彼のスタイルの核心です。派手な技巧よりも、楽曲全体を見据えたプレイが魅力となっています。
YouTubeでKENTAのプレイをチェック → こちら
使用アンプ一覧と特徴【WANIMA・KENTA】
KENTAはライブおよびレコーディングにおいて、Gallien-Kruegerのアンプを主軸に据えています。特に1001RB-IIは、パンチのある低域と明瞭な高域が特徴で、ロックサウンドに適したモデルです。ライブではキャビネットと組み合わせて大音量を確保しつつ、レコーディングではDIを介してクリーンな信号を取り込むことが想定されます。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001RB-II | Gallien-Krueger | WANIMA | KENTA | メインアンプヘッド、700W出力 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Neo 412 | Gallien-Krueger | WANIMA | KENTA | 4×12キャビネット | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Backline 600 | Gallien-Krueger | WANIMA | KENTA | リハーサル・小規模ライブ用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用ベースの種類と特徴【WANIMA・KENTA】
KENTAのメイン機はESP製シグネチャーモデル「助平」で、プレシジョンベースタイプのピックアップ構成を持っています。太く力強いサウンドが特徴で、パンクロックに最適な音色を提供します。カラーバリエーションも豊富で、ライブでは複数本を使い分けている様子が確認されています。サブ機としても同型の別カラーを使用していると想定されます。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | ベースの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 助平 KENTA Model | ESP | WANIMA | KENTA | プレシジョンベースタイプ | シグネチャーモデル、メイン機 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| 助平 White | ESP | WANIMA | KENTA | プレシジョンベースタイプ | ホワイトカラー、サブ機 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| 助平 Black | ESP | WANIMA | KENTA | プレシジョンベースタイプ | ブラックカラー | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Precision Bass | Fender | WANIMA | KENTA | プレシジョンベース | 初期使用機材と想定 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用エフェクターとボード構成【WANIMA・KENTA】
KENTAのエフェクターボードはシンプルな構成で、ベース本体からダイレクトボックス、そしてアンプへと接続される流れが基本です。必要最小限の機材で確実なサウンドを作るスタイルを採用していると想定されます。Avalon Design U5などの高品質なDIを使用することで、クリーンで明瞭な信号をPAシステムやレコーディング機器に送っています。オーバードライブやコンプレッサーも必要に応じて使用していると考えられます。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | エフェクターの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U5 | Avalon Design | WANIMA | KENTA | ダイレクトボックス | 高品質DI/プリアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bass Driver DI | Tech 21 | WANIMA | KENTA | プリアンプ/アンプシミュレーター | 汎用DI/オーバードライブ機能 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| TU-3 | BOSS | WANIMA | KENTA | プリアンプ/アンプシミュレーター | クロマチックチューナー | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【WANIMA・KENTA】
基本EQ設定
KENTAの音作りは、ミドルレンジを中心にした設定が基本です。Gallien-Kruegerのアンプでは、低域を適度に持ち上げつつ、200Hz〜500Hz付近のローミッドを強調することで、バンドサウンドの中で埋もれない存在感を確保しています。高域は明瞭さを出すために軽くブーストしますが、耳障りにならない程度に抑えていると想定されます。ピック弾きのアタック感を活かすため、コンプレッサーは浅めにかけるか使用しない場合もあります。
楽曲別の使い分け
アップテンポなパンクナンバーでは、ピックの強いアタックを活かした攻撃的なサウンドを優先します。一方、ミドルテンポの楽曲では、若干ゲインを落として音の輪郭を整え、ボーカルや他の楽器とのバランスを重視していると考えられます。ライブではエネルギー重視、レコーディングではクリーンさと明瞭さのバランスを取った設定が使い分けられているでしょう。
ミックスでの工夫
レコーディングやミックスの段階では、DI信号とアンプからのマイク信号をブレンドすることで、太さと明瞭さを両立させていると想定されます。DI信号は低域の芯を確保し、アンプ信号は空気感とミドルの質感を加える役割を果たします。EQでは不要な超低域をカットし、バスドラムとの棲み分けを明確にすることで、ミックス全体の見通しを良くしています。
比較的安価に音を近づける機材【WANIMA・KENTA】
KENTAのサウンドを予算を抑えて再現するには、プレシジョンベースタイプの楽器とGallien-Krueger系のアンプを選ぶことがポイントです。初心者でも扱いやすいエントリーモデルや中古品を活用することで、十分に近いサウンドを得られます。
| 種類 | 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | Player Precision Bass | Fender | WANIMA | KENTA | コスパの良いPベース | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | BB434 | YAMAHA | WANIMA | KENTA | 太いサウンド、中価格帯 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | MB210 | Gallien-Krueger | WANIMA | KENTA | コンボアンプ、自宅練習に最適 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | Rumble 500 | Fender | WANIMA | KENTA | 軽量、パワフル、ライブ向け | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| DI | REDDI | A-Designs | WANIMA | KENTA | 真空管DI、温かみのあるサウンド | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| DI | DI-1 | BOSS | WANIMA | KENTA | 低価格、初心者向けDI | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
総括まとめ【WANIMA・KENTA】
KENTAの音作りの本質は、シンプルかつ力強いサウンドを追求する姿勢にあります。プレシジョンベースタイプの楽器とGallien-Kruegerアンプの組み合わせは、パンクロックに必要な太さと明瞭さを兼ね備えており、バンドアンサンブルの中でしっかりと存在感を示します。高価な機材を多数揃えるよりも、基本となる楽器とアンプの特性を理解し、EQ設定やピッキングの強弱でサウンドをコントロールすることが重要です。
再現のポイントとしては、ミドルレンジを中心としたEQ設定と、ピックによる強いアタックを活かすプレイスタイルが挙げられます。コンプレッサーを浅めにかけるか使用しないことで、ダイナミクスを保ちつつエネルギッシュな演奏を実現できます。DI信号とアンプ信号のブレンドは、レコーディングやライブPAにおいて音質の幅を広げる有効な手段です。
機材に頼りすぎないコツは、まず自分の手と楽器だけでどれだけ音色を変えられるかを探求することです。ピッキングの位置や強さ、右手のミュートなど、基本的なテクニックを磨くことで、エフェクターに頼らずとも多様な表現が可能になります。KENTAのように、楽曲全体を見据えた音作りを心がけることで、バンドサウンドにおけるベースの役割を最大限に発揮できるでしょう。
初心者の方は、まずプレシジョンベースタイプの楽器と信頼できるアンプを手に入れ、そこから自分の好みに合わせて少しずつ機材を追加していくアプローチをお勧めします。KENTAのサウンドは決して複雑ではありませんが、その分だけ基本に忠実であり、長く使える音作りの指針となるはずです。
本記事参照サイト【WANIMA・KENTA】
本記事は下記公式サイト等も参照させていただいております。