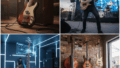上杉研太・SUPER BEAVER 始めに
上杉研太は、東京都出身のロックバンドSUPER BEAVERのベーシストとして、バンドの低音を支える重要な存在です。1987年2月14日生まれの彼は、メンバーの中でも最年長であり、バンドのサウンドに深みと安定感をもたらしています。SUPER BEAVERは2005年に結成され、渋谷のライブハウスを中心に活動を開始し、2013年にメジャーデビューを果たしました。上杉のベースプレイは、力強いピッキングと正確なリズムキープが特徴で、バンドの楽曲に欠かせない土台を形成しています。
彼のプレイスタイルは、ロックバンドとしての骨太なサウンドを支えつつ、メロディアスなフレーズも織り交ぜる柔軟性を持っています。代表曲「人として」や「ラブソング」では、シンプルながらも存在感のあるベースラインが楽曲全体を引き締めています。また、ライブでは観客を熱狂させるエネルギッシュなパフォーマンスも魅力の一つです。上杉は機材選びにもこだわりを持ち、特にフレットレスベースの使用など、独自のサウンドアプローチを追求しています。彼の音作りは、バンドの楽曲性を最大限に引き出すための工夫が随所に見られます。
上杉研太の音楽性は、テクニカルなプレイよりもグルーヴ感と楽曲への貢献を重視する姿勢に表れています。SUPER BEAVERの楽曲は、ボーカル渋谷龍太の熱いメッセージ性と相まって、多くのファンの心を掴んでいます。上杉のベースは、そのメッセージを支える確固たる基盤として機能しており、バンドサウンドに不可欠な要素となっています。フレットレスベースを自ら製作するなど、機材への探求心も旺盛で、常に理想のサウンドを追い求める姿勢が印象的です。
YouTubeで上杉研太のプレイをチェック → こちら
使用アンプ一覧と特徴【SUPER BEAVER・上杉研太】
上杉研太のアンプセッティングは、ライブとレコーディングで使い分けを行いながら、一貫してパワフルで存在感のある低音を追求しています。特にOrange製のアンプを愛用しており、その独特の中域の押し出しとタイトな低音が、SUPER BEAVERのロックサウンドに最適なキャラクターを提供しています。ライブではヘッドアンプとキャビネットを組み合わせたスタックスタイルを採用し、大音量でも音像が崩れない安定性を確保しています。
レコーディングにおいては、楽曲ごとに異なるアンプを試すこともあるとされ、曲の雰囲気に合わせた音色選びを重視しています。アンプのEQ設定は比較的フラットに近い状態から微調整を加え、ベース本体の音色特性を活かすアプローチを取っていると想定されます。また、アンプシミュレーターやDIボックスを併用することで、レコーディングにおける音作りの幅を広げています。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD200 MK3 | Orange | SUPER BEAVER | 上杉研太 | メインヘッドアンプ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| OBC810 | Orange | SUPER BEAVER | 上杉研太 | キャビネット | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Terror Bass | Orange | SUPER BEAVER | 上杉研太 | コンパクトヘッド | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| OBC410 | Orange | SUPER BEAVER | 上杉研太 | 4×10キャビネット | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用ベースの種類と特徴【SUPER BEAVER・上杉研太】
上杉研太は複数のベースを使い分けており、楽曲の雰囲気や表現したいニュアンスに応じて選択しています。メインで使用しているのはフェンダー系のプレシジョンベースとジャズベースで、ロックバンドの定番として安定した音色とプレイアビリティを提供しています。プレシジョンベースは太く図太い低音が特徴で、バンドの楽曲において力強いサウンドを求める場面で活躍しています。一方、ジャズベースは2つのピックアップによる音色の多様性があり、よりアタック感のあるサウンドが必要な楽曲で使用されています。
特筆すべきは、上杉が自らフレットレスベースを製作して使用している点です。フレットレスベースは、フレット付きベースとは異なる滑らかで温かみのある音色が特徴で、楽曲に独特の表情を加えることができます。上杉はPsychederhythmでフレットレス化の過程を公開しており、DIY精神と機材へのこだわりが伺えます。フレットレスベースは特定の楽曲やレコーディングで効果的に使用され、SUPER BEAVERのサウンドに新たな色彩を与えています。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | ベースの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision Bass | Fender | SUPER BEAVER | 上杉研太 | プレシジョンベース | メイン使用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Jazz Bass | Fender | SUPER BEAVER | 上杉研太 | ジャズベース | サブ使用 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Fretless Bass | 自作改造 | SUPER BEAVER | 上杉研太 | フレットレスベース | 自らフレットレス化 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| American Professional Precision Bass | Fender | SUPER BEAVER | 上杉研太 | プレシジョンベース | 現行モデル想定 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| American Professional Jazz Bass | Fender | SUPER BEAVER | 上杉研太 | ジャズベース | 現行モデル想定 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
使用エフェクターとボード構成【SUPER BEAVER・上杉研太】
上杉研太のエフェクターボードは、シンプルかつ実用的な構成となっています。シグナルチェーンは、ベース本体からチューナーを経由し、ダイナミクス系のコンプレッサーで音を整え、その後プリアンプやオーバードライブで音色を調整し、最終的にアンプへと送られます。必要に応じてスイッチングシステムを使用し、ライブ中のエフェクトの切り替えをスムーズに行っています。Free The Tone製のスイッチャーやパワーサプライを使用することで、安定した電源供給とノイズレスな信号経路を確保しています。
上杉のエフェクター選びは、音質劣化を最小限に抑えつつ、必要な音色変化を得ることを重視しています。特にプリアンプやDIボックスは、アンプへの入力段階で音色を整える重要な役割を担っており、ライブとレコーディングの両方で活用されています。オーバードライブやディストーションは楽曲の盛り上がりやアクセントとして使用され、全体としてベース本来の音色を活かしつつ、表現力を高める設計となっています。
| 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | エフェクターの種類 | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARC-3 | Free The Tone | SUPER BEAVER | 上杉研太 | スイッチングシステム | エフェクト切替 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| PT-3D | Free The Tone | SUPER BEAVER | 上杉研太 | パワーサプライ | 電源供給 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bass Compressor | Boss | SUPER BEAVER | 上杉研太 | コンプレッサー | ダイナミクス調整 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bass Driver DI | Tech 21 | SUPER BEAVER | 上杉研太 | プリアンプ/アンプシミュレーター | 音色調整 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Bass Overdrive | Boss | SUPER BEAVER | 上杉研太 | オーバードライブ | 歪み系 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Tuner TU-3 | Boss | SUPER BEAVER | 上杉研太 | チューナー | チューニング | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| Active DI Box | Free The Tone | SUPER BEAVER | 上杉研太 | ダイレクトボックス | ライン出力 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
音作りのセッティング・EQ・ミックスの工夫【SUPER BEAVER・上杉研太】
基本EQ設定
上杉研太の基本的なEQ設定は、低域をしっかりと確保しつつ、中域の存在感を重視したバランスとなっています。アンプのEQは比較的フラットに近い状態からスタートし、楽曲やライブ会場の音響特性に応じて微調整を加えるアプローチを取っています。低域は100Hz前後をやや持ち上げることで、バンドサウンドの土台となる太い音を確保しています。中域は400Hz〜800Hz付近を調整することで、他の楽器と混ざり合いながらもベースの存在感を保つようにしています。
高域については、アタック感とピック弾きの明瞭さを出すために、3kHz〜5kHz付近を適度にブーストすることがあります。ただし、過度に高域を強調すると耳障りになるため、楽曲の雰囲気に応じて慎重に調整しています。ベース本体のトーンコントロールとアンプのEQを組み合わせることで、柔軟な音色変化を実現しています。また、コンプレッサーを使用することで、ダイナミクスを整え、演奏中の音量のばらつきを抑えています。
楽曲別の使い分け
SUPER BEAVERの楽曲は、バラードからハードロックまで幅広いスタイルを持っているため、上杉は楽曲ごとに音作りを調整しています。バラード系の楽曲では、温かみのある丸い音色を作るために、トーンをやや絞り、低域を中心としたサウンドメイキングを行います。一方、アップテンポのロックナンバーでは、アタック感を強調し、ピッキングのニュアンスが伝わるよう高域を持ち上げています。
フレットレスベースを使用する楽曲では、独特の滑らかな音色を活かすために、EQをよりフラットに近い設定にし、ベース本来の音色を前面に出すようにしています。また、ライブでは曲間でエフェクターのオン・オフを切り替えることで、楽曲ごとのキャラクターを明確に表現しています。スイッチングシステムを活用することで、素早く確実な切り替えが可能となり、演奏に集中できる環境を整えています。
ミックスでの工夫
レコーディングにおけるミックスでは、ベースがバンド全体の低音の土台となるよう、キックドラムとの棲み分けが重要となります。上杉のベースサウンドは、キックドラムよりもやや高めの帯域に存在感を持たせることで、両者が競合せずに共存できるようにしています。EQでは、60Hz以下の超低域をカットし、80Hz〜100Hz付近でベースの芯を作り、200Hz〜500Hz付近でボディ感を加えています。
また、ギターとの関係性も考慮し、ベースとギターが互いに干渉しない周波数帯域を見つけることが重要です。ギターが中域から高域を担当するのに対し、ベースは低域から中低域を支える役割を果たすことで、バンド全体のサウンドに厚みが生まれます。コンプレッサーを適切に使用することで、音量のばらつきを抑え、ミックス内でのベースの存在感を安定させています。リバーブやディレイは控えめに使用し、ベースの輪郭を保つようにしています。
比較的安価に音を近づける機材【SUPER BEAVER・上杉研太】
上杉研太のサウンドに近づけるためには、必ずしも高額な機材が必要というわけではありません。エントリーモデルやコストパフォーマンスの高い機材を選ぶことで、初心者でも彼の音作りの方向性を体験することができます。ここでは、予算を抑えつつも上杉のサウンドに近づける機材を紹介します。ベース本体としては、スクワイアやフェンダーのメキシコ製など、コストパフォーマンスの高いプレシジョンベースやジャズベースがおすすめです。
アンプについては、小型のコンボアンプでもOrangeのCrushシリーズなど、同ブランドのキャラクターを持つ製品を選ぶことで、サウンドの方向性を掴むことができます。エフェクターについては、BossやBehringerなどの定番ブランドから、コンプレッサーやオーバードライブを選ぶと良いでしょう。これらの機材を組み合わせることで、上杉研太のサウンドのエッセンスを手頃な価格で再現することが可能です。
| 種類 | 機材名 | メーカー | アーティスト | ベーシスト | 備考 | Amazon | 楽天 | Yahoo! | 石橋楽器 | サウンドハウス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベース | Affinity Precision Bass | Squier | SUPER BEAVER | 上杉研太 | エントリーモデル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | Affinity Jazz Bass | Squier | SUPER BEAVER | 上杉研太 | エントリーモデル | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| ベース | Player Precision Bass | Fender | SUPER BEAVER | 上杉研太 | メキシコ製 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | Crush Bass 50 | Orange | SUPER BEAVER | 上杉研太 | 小型コンボ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | BC-1X Bass Comp | Boss | SUPER BEAVER | 上杉研太 | コンプレッサー | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | ODB-3 Bass Overdrive | Boss | SUPER BEAVER | 上杉研太 | オーバードライブ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| エフェクター | Sansamp Bass Driver DI V2 | Tech 21 | SUPER BEAVER | 上杉研太 | プリアンプDI | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
| アンプ | Rumble 40 | Fender | SUPER BEAVER | 上杉研太 | 練習用コンボ | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 | 検索 |
総括まとめ【SUPER BEAVER・上杉研太】
上杉研太の音作りの本質は、バンドの楽曲を最大限に活かすことにあります。彼のベースプレイは派手なテクニックよりも、確実なリズムキープとグルーヴ感を重視しており、SUPER BEAVERのロックサウンドを支える重要な土台となっています。機材選びにおいても、流行や高額な製品に流されることなく、自分の音楽性に合ったものを選ぶ姿勢が印象的です。フレットレスベースを自ら製作するなど、DIY精神と探求心を持ち続けている点も、彼の音楽に対する真摯な姿勢を表しています。
上杉のサウンドを再現する際のポイントは、まずベース本体の音色特性をしっかりと理解することです。プレシジョンベースやジャズベースといった定番モデルを選び、それぞれの持ち味を活かす音作りを心がけましょう。アンプのEQは過度に持ち上げるのではなく、楽曲全体のバランスを考えながら調整することが重要です。エフェクターについても、必要最小限の構成で音色を整え、ベース本来の音を損なわないようにすることが大切です。
初心者がこのサウンドに近づくためには、まず基本的な演奏技術を磨くことが最優先です。正確なリズムキープ、安定したピッキング、適切なミュート技術など、ベーシストとしての基礎をしっかりと身につけることで、機材の性能を十分に引き出すことができます。高額な機材を揃える前に、手持ちの機材で様々な設定を試し、自分の音を見つける過程を楽しむことが重要です。
機材に頼りすぎず、プレイヤー自身の感性と技術を磨くことこそが、上杉研太のようなベーシストに近づく最短の道です。機材はあくまで表現のための道具であり、最終的には演奏者の音楽性とタッチが音色を決定します。彼のプレイから学ぶべきは、楽曲への献身的な姿勢と、バンド全体の中での自分の役割を理解した上での音作りです。この基本的な考え方を大切にしながら、自分なりのサウンドを追求していくことが、ベーシストとしての成長につながるでしょう。
本記事参照サイト【SUPER BEAVER・上杉研太】
本記事は下記公式サイト等も参照させていただいております。